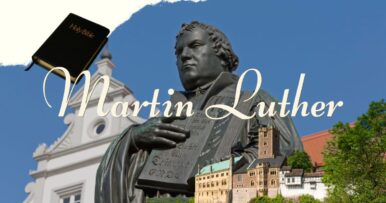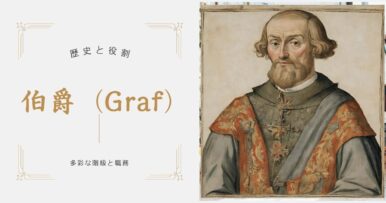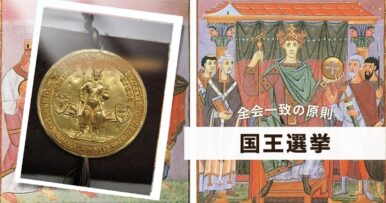方伯をラテン語で表現すると、lantgravius または comes terrae といい、諸侯の称号で「伯爵」の称号よりも上になります。
遅くとも中世後期以降の神聖ローマ帝国では、「方伯」、「辺境伯」および一部の「宮中伯」は帝国諸侯の一員であり、事実上、公爵と同等の扱いを受けていました。
 城山塔子
城山塔子1815年以降のヘッセン=カッセル方伯は、王室と同じように「陛下(Hoheit)」と呼ばれていたよ。



ヘッセン方伯は、プロイセンの時代に大公の地位に昇格したのよね
ヘッセン方伯は、現在大公や選帝侯の称号を失っていますが、方伯の称号を使い続けています。
本記事では、方伯の爵位が誕生した経緯と、代表的な方伯家を紹介します。
方伯の誕生


User:Acoma, Public domain, via Wikimedia Commons
12世紀初頭に帝国南西部(アルザス、トゥールガウ、アールガウ、ブライスガウ地域など)で、おそらく帝国の領地とその管理を任された伯爵につけられた称号として登場しました。



レガリアの管理も任されていたけど、帝国諸侯の地位に昇格することは稀だったよ。
方伯は国王あるいは皇帝の役人で、元々は帝国内に配置され、ドイツ国王から与えられた封土で上位の司法権を持っていました。旧伯爵権が著しく分断されていた地域で、初期地方伯の後をついですべての自由民と貴族の上の司法身分。
公爵、司教、宮中伯の仲介は受けません。
これまでの部族公爵の権力を弱め、帝国の正当性なしに拡大しようとする企てを阻止するために行われた政治的創造物。古い王権を守る役割を担っていました。
方伯という言葉は、都市管理を任された城伯(Burggraf)と区別するためにも使用されました。
ヘッセン方伯とチューリンゲン方伯


August Erich, Public domain, via Wikimedia Commons
ヘッセン方伯家とチューリンゲン方伯家は例外的な存在です。
中世中期で最も重要なのはチューリンゲン方伯です。
チューリンゲンではルドヴィング家(Ludwing)が土地を所有し、伯爵領権や荘園権並びにその他レガリアを重要視していました。
計画的な領土政策により、ドイツ中部のヘッセン・ニーダーザクセン・チューリンゲン地方にチューリンゲン方伯領を築き上げました。しかし1247年に大陸国王ハインリッヒ・ラスペ(Heinrich Raspe)を最後に男系が途絶えてしまいました。
ルドヴィング家の居城


これにより、他の自由民や貴族に対する方伯の司法権を利用して、実際の領地以外の領後件を強化し、最終的に方伯領で準公爵的な権利を行使し、帝国諸侯に任命されるに至りました。



帝国諸侯に上り詰めたのは、ルドヴィング家だけかも
他の方伯位の貴族たちの重要性は低く、方伯位に基づく帝国諸侯の地位を手にすることはなく、せいぜい伯爵権にもとづいているに過ぎませんでした。
方伯の称号は聖エリザベートの子孫を通じてテューリンゲンからヘッセンへと移る一方、チューリンゲンではヴェッティン公爵家が引き継いだ後、ザクセン公の称号に覆われてしまいました。
1292年、皇帝により新しく設立されたヘッセン方伯は帝国諸侯として認可されました。
ヘッセン方伯家
- ヘッセン=ブラバント(Hessen-Brabant)
-
19世紀まで方伯位を保持していました。
- ヘッセン=カッセル(Hessen-Kassel)
-
1803年、神聖ローマ帝国の皇帝によって選帝侯の爵位を授爵。選帝侯を名乗るようになります。
- ヘッセン=ダルムシュタット(Hessen-Darmstadt)
-
ナポレオン1世によって大公に昇格。大公と名乗るようになります。
- ヘッセン=ホンブルク(Hessen-Homburg)
-
1866年に断絶すると、ヘッセン=ダルムシュタット家に引き継がれます。しかしプロイセン・オーストリア戦争により、プロイセンに併合されてしまいます。
あわせて読みたい
 バート・ホンブルク城(Landgrafenschloss Bad Homburg)の歴史と見どころを紹介!―プロイセン王家の夏… バート・ホンブルク城は、フランクフルト(Frankfurt am Main)の北にある小さな温泉街バート・ホンブルク・フォン・デア・ヘーエ(Bad Homburg v.d.Höhe)にある城で、…
バート・ホンブルク城(Landgrafenschloss Bad Homburg)の歴史と見どころを紹介!―プロイセン王家の夏… バート・ホンブルク城は、フランクフルト(Frankfurt am Main)の北にある小さな温泉街バート・ホンブルク・フォン・デア・ヘーエ(Bad Homburg v.d.Höhe)にある城で、…
ヘッセン家では1920年以降選帝侯並びに大公の称号を失いましたが、今現在、王子やヘッセン方伯の名前を再び使用するようになっています。
各家の当主がヘッセン方伯として公の場に登場し、他の家族すべて自分をヘッセン王子または王女として公の場では呼ばれます。
ロイヒテンベルク(Leichtenberg)家


planola, CC BY 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by/3.0, via Wikimedia Commons
ロイヒテンベルク家は、1196年から1646年まで存在していた方伯家。レーゲンスブルク(Regensburg)城伯家が断絶した後、レーゲンスブルク城伯の資産を受け継いで誕生しました。
ロイヒテンベルク家は1158年に伯爵に昇格し、1196年に伯爵となりました。15世紀には帝国諸侯として帝国議会に議席を持つまでになっています。
1646年に断絶すると、その領土は親戚筋のバイエルン公爵アルプレヒト六世(Albrecht VI.)に引き継がれ、ロイヒテンベルク公を名乗るようになりました。