騎士叙任式は、中世ヨーロッパの騎士道文化において、若い戦士が正式な騎士として認められる最も重要な通過儀礼です。この儀式を通して、若者は騎士身分とそれに伴う権利・義務が与えられました。
この儀式で新たに騎士となる者は、騎士としての精神(騎士道)を誓います。
騎士を目指す少年が正式な騎士(Ritter)となるためには、まずページ(Page:騎士見習い、小姓)として主君に仕え、礼儀作法や武術などの修行を積まなければなりません。
主君に実力が認められると、20歳前後で「刀礼(Rittershclag)」=騎士叙任式を経て、晴れて騎士として認められます。
 城山塔子
城山塔子刀礼は、もともと武器を持つことができる自由民男子に与えられた資格だったんだけど、時代が進むにつれて「騎士の成人式」として位置づけられていったよ。
本記事では、中世騎士階級の成人式である騎士叙任式の歴史的背景と儀式の流れについて紹介します。
騎士叙任式の変遷と宗教的意義


騎士叙任式の起源は、8世紀頃のフランク王国にまで遡ります。
当初は実用的で質素な任命儀式でしたが、11世紀の十字軍時代を経て、キリスト教会の影響を強く受けた宗教的な色彩を帯びるようになりました。
騎士たちの暴力性を抑えるために、キリスト教会が儀式に宗教性を加えていったのです。
キリスト教会にとって、戦争好きな騎士は頭痛の種。
叙任式は、荒々しい騎士をおとなしくさせるために、キリスト教と結びついた儀式へと変貌させました。


12世紀から13世紀になると、騎士叙任式は最も洗練された形式へと確立しました。この時期には騎士道ロマンスの影響もあり、儀式はより装飾的で象徴的な要素を含むようになりました。
騎士になるための儀式にミサが取り入れられ、宗教的に厳粛化していきます。
騎士叙任式の流れ


騎士叙任式は地域や時代によって形式が異なりますが、特にフランスで洗練され、のちにドイツなどにも広まりました。
ドイツでは、フランス宮廷で教育を受けたカール四世が神聖ローマ帝国に輸入する形で14世紀になって取り入れられ、広まります。
事前準備
騎士叙任式の前には、通常数週間から数ヶ月の準備期間が設けられました。
騎士の候補者たちは叙任式に向けて、以下のような準備をし、その日を待ちます。
物理的準備
- 武器と防具
-
剣を帯び、拍車を身につける儀式があります。儀式に用いる剣と防具を準備しなければなりません。
- 儀式用の衣装
-
騎士叙任式はハレの日です。豪華な衣装を身に着けたいものです。



成人式に豪華な衣装を着るのは、古今東西問わないのね。
精神的準備
- 騎士道に関する教育
-
騎士らしい振る舞いについては幼い頃より教育されています。叙任式ではその成果を示さなければなりません。
あわせて読みたい
 中世ヨーロッパ貴族の子どもの教育とはどんなものだったのか 昔の日本と同様に、ヨーロッパでも基本的に上流階級の母親は自分で母乳を与えず、乳母に世話をさせます。 子どもの教育が本格的に始まるのは7歳から。小学生になる年齢…
中世ヨーロッパ貴族の子どもの教育とはどんなものだったのか 昔の日本と同様に、ヨーロッパでも基本的に上流階級の母親は自分で母乳を与えず、乳母に世話をさせます。 子どもの教育が本格的に始まるのは7歳から。小学生になる年齢…
叙任式当日
厳粛なその儀式は、前日の夜から始まります。ページは紋章と武器を教会の祭壇の上に置き、沐浴して身を清めます。その後、祭壇に向かって、徹夜で祈りを捧げます。
騎士としての決意を固める時間とされました。


夜明けとともに、ページは祈りを捧げます。神、君主、教会への忠誠、弱者の保護、不正との戦いなど、騎士としての行動規範(騎士道)を守ることを誓います。
この時、白いチュニックやマントを着用し、純血と神への献身を示しました。
当初このようなミサはなく、騎士とキリスト教が結びつくようになってこのような儀式が取り入れられるようになりました。



騎士が「神の前で誓いを立てる存在」になるよう、教会が努力した結果
騎士の最も重要な象徴とも言える剣が、司祭により祝福されます。



これらの武器は単なる戦闘道具ではなく、神の意志を実行するための神聖な道具として位置づける意味合いがあるよ。
ページは神と主君、民衆の前で騎士として、以下のことを誓います。
- 教会と信仰の守護
- 弱者と非力な者の保護
- 神と主君への中世
- 正義と真実への献身



歴史を振り返れば、これらが守られているとは思えないけどね。
この儀式で最も重要な瞬間、刀礼(アコレード)。


初期の頃は首に手を当てるだけの刀礼が一般的でした。剣による刀礼はかなりあとになってからです。
男らしさと成熟を確認するものです。
刀礼は騎士として受ける最後の打撃であり、これ以降は不名誉な打撃を受けてはならない、あるいは騎士としての自覚を促すといった意味合いがあったとされています。



本気で叩く主君もいれば、そっと触れるだけの人もいたよ。時代と地域で大きな違いがあったよ。
このとき、騎士になる者は主君に対して願い事をします。不当なものでない限り、たいてい受け入れられました。
現在のイギリスでは、国王による叙勲制度として騎士叙任式の伝統が継続されています。これはずっと後になって始まったもので、功績のあった市民に対して「サー」や「デイム」の称号が授与されます。
ページから騎士になったものに対し、装身具が授与されます。
主君自ら見習いであったものに剣をはかせ、兜や盾、槍を授けます。
- 拍車(馬に乗る騎士の象徴)
- 剣帯
- 騎士のマント
- (指輪や首飾り)
特に剣帯は騎士の象徴であり、騎士でない者は剣を鞍に固定させるのが一般的でした。
儀式後は、新しい騎士の誕生を祝って盛大な宴やや馬上槍試合(トーナメント)が行われるのが通例です。
中世騎士物語の『ニーベルンゲンの歌』でも、ジークフリートが騎士になった際に、盛大な祝賀会と馬上槍試合が開かれた様子が描かれています。
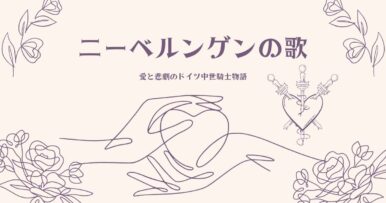
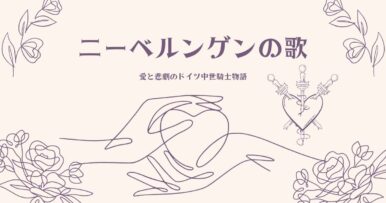


騎士叙任式を受けられない者たち


中世後期、騎士階級になれるのは騎士の家系出身であることが前提条件でした。
さらに、騎士になるには、自らの装備(馬・鎧・武器・従者)を自費で準備する必要があります。そのため、裕福でなければ叙任を受けることすら叶わなかったのです。
家が貧しく、馬、鎧、武器、従者といった騎士に必要なものを維持する余裕がない者たち……。
貧者は騎士になれないまま、騎士の資格も爵位ももたないページのまま、一生を終えることもありました。



父たちは必要な道具を揃えてくれそうな裕福な教育係(君主:パトロン)を探したんだよ。
貧しい家庭の出身者はページのまま年を重ね、騎士にも貴族にもなれないまま生涯を終えることもありました。
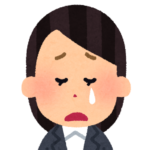
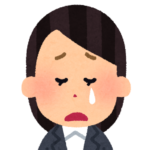
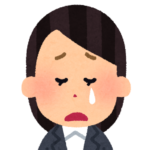
ページのまま一生を終えるのは、悲しいね。
憧れの騎士になっても、城なし、士官先なし、コネなしの場合、厳しい生活が待っていました。


騎士叙任式の広がりと「盾仲間」
騎士の頭数が必要な戦争前後や、大きな祝い事の際に、叙任式を集団で行うことがよくありました。
詩人でミンネゼンガーとしても有名なウルリッヒ・フォン・リヒテンシュタイン(Ulrih von Lichtenstein)も、主君のオーストリア公の令嬢の婚礼の際に、250人の若者たちと一緒に騎士になった逸話が残っています。
共に叙任を受けた同期たちを「盾仲間(Schildgesellen)」と呼び、一生変わらぬ友情を結びました。


まとめ


Ruud Mol/Ministerie van Defensie, CC0, via Wikimedia Commons
実は多くの国の軍隊で行われる任官式や宣誓式に騎士叙任式の影響を見て取れます。
騎士叙任式は、中世ヨーロッパの社会、宗教、軍事、文化が複雑に絡み合った独特の儀式。この儀式は、個人の成長と社会的地位の確立を象徴するとともに、中世社会の価値観と理想を具現化したものです。
中世社会における騎士の役割と理想を象徴する、荘厳で重要な儀式でした。
現代においても、騎士叙任式の精神は様々な形で受け継がれており、責任感、奉仕の精神、そして道徳的な価値観の重要性を想起させます。
また、ファンタジー作品などでも騎士が誕生する場面として描かれることが多いです。
中世の騎士叙任式を理解することで、現代社会における儀式や通過儀礼の意味についても、より深く考察することができるのではないでしょうか。





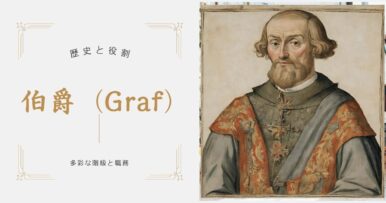
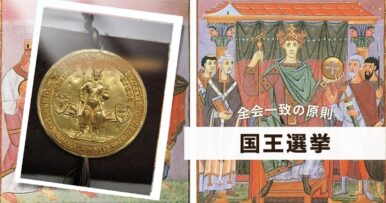






コメント