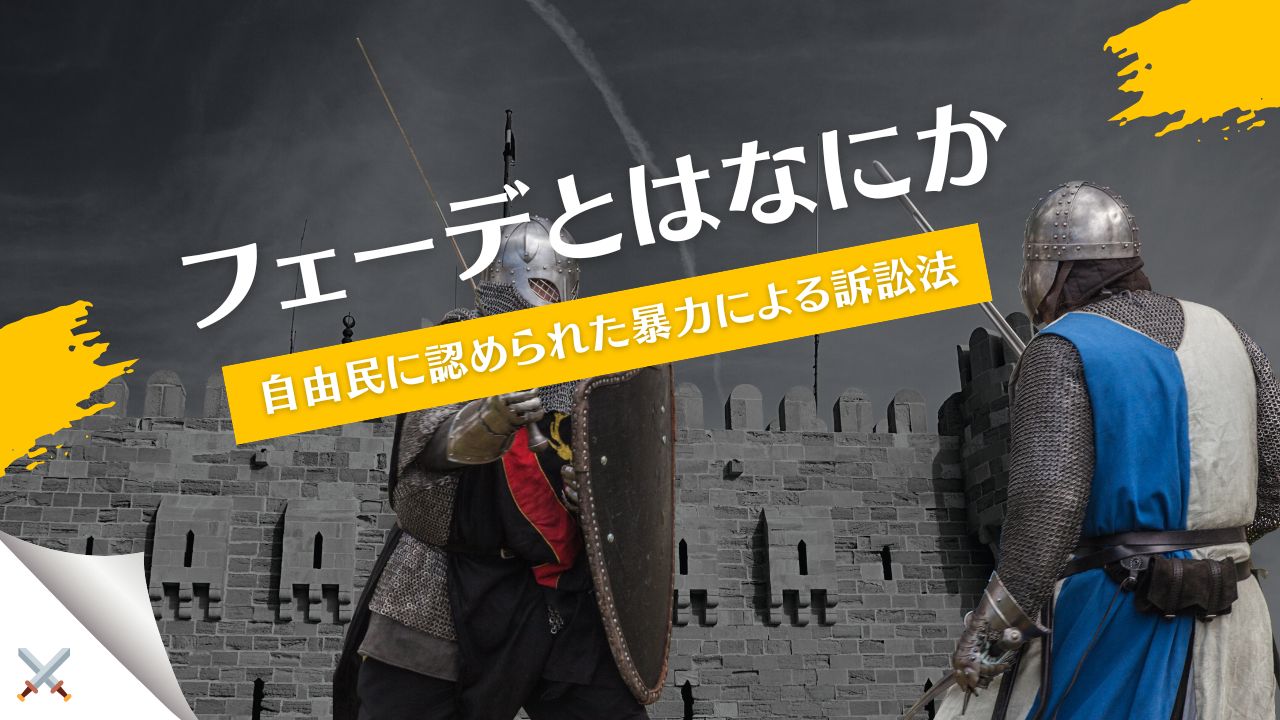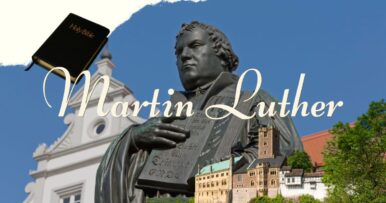フェーデは決闘の一種です。
 城山塔子
城山塔子フェーデは確執と表現されることがありますが、ここではフェーデのまま使用します。
中世前期、フェーデは加害者に対し自由民である被害者、またはその一族が暴力でもって加害者に復讐する訴訟法でした。



仇討みたいなものなのかな?
ニーベルンゲンの詩といったミンネザングの中でもフェーでは重要な役割をしており、血の報復(Blutfehde)という形で描かれています。
中世では、自分の権利は自分で確保して守らなければならず、さもなければ権利を失ってしまう。
フェーデは自分の権利を守るための戦いでした。



土地持ちの貴族に認められた、小さな戦争のことです。
小さな戦争とはいえ、時に大規模な戦争に発展することはあります。


フェーデとは何か
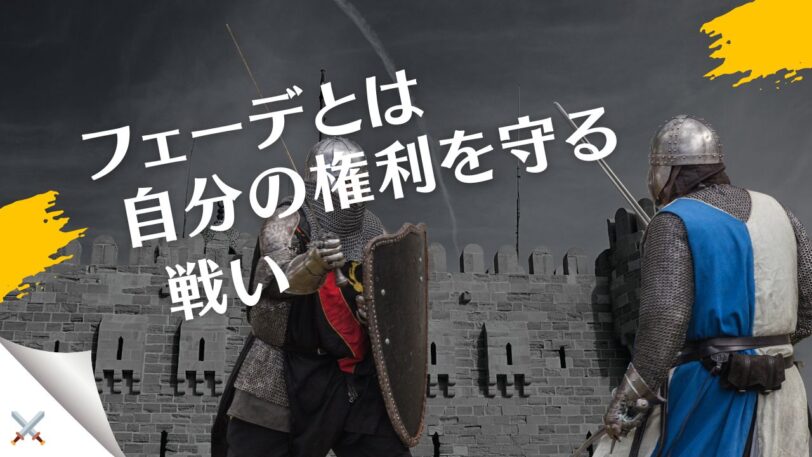
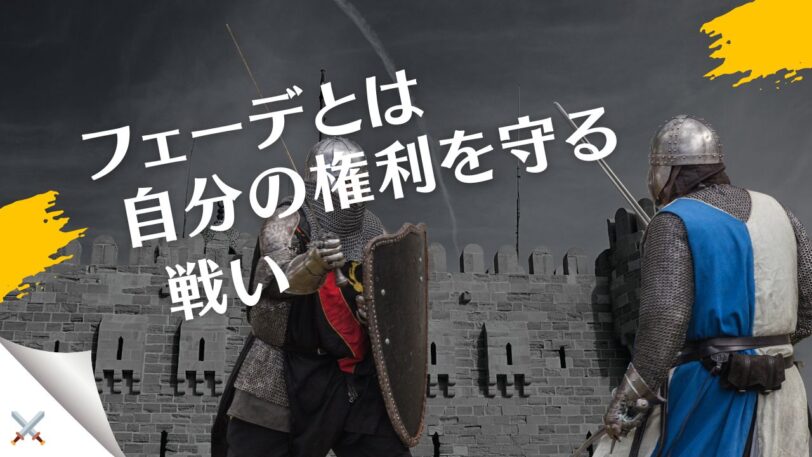
第三者機関である司法機関を介することなく行われる行為で、不当な自助救済ではなく認められた行為。
まだ証拠書類といったものがなかった時代。複雑な法律関係で正当な判断を下し、執行する裁判所を見つけることは困難でした。



裁判の判決に強制力がないことが多かったんだよ
裁判所はあっても強制力はない。警察もない。
そんな時代にフェーデが自分の権利を守るための法的な救済措置。
フェーデとは、裁判所に頼らず加害者と被害者の間で直接解決することを規制した法制度のこと。
フェーデを行うかどうかは、本人とその一族に任せられていました。
フェーデは宣戦布告が行われたあと、決まった場所、決まった建物で行われます。
自分の主張を通すために、城の建設は必須。



野戦よりも攻城戦がほとんどだったからね。
フェーデは相手側に犠牲者を出すことではなく、相手に自分の法的主張を認識させ、和解に持ち込むことを目的としていました。
とはいえ、
略奪、農作物の焼却、家屋の破壊、果樹の伐採、家畜の殺戮、強盗、城の占拠や制服は合法。
一般的にフェーデは武器を持つ能力のあるものであれば、農民でも行うことが認められていましたが、12世紀の始めには騎士社会と都市のみに適用されるようになりました。ただし、両親が騎士家系である必要があります。
フェーデの歴史
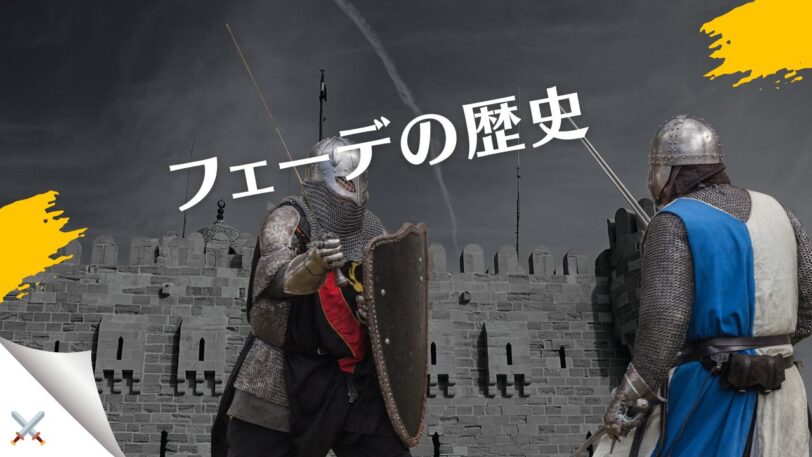
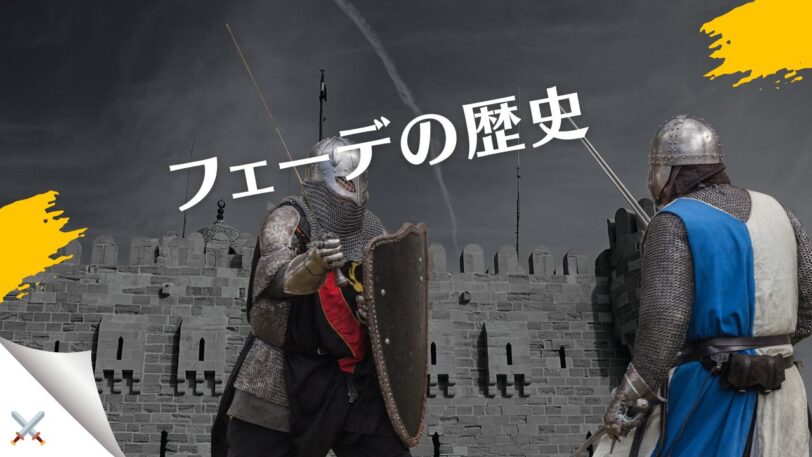
古代
フェーデの起源はゲルマニア時代にみることができます。
まだ国家という概念は存在せず、部族や氏族という単位で組織運営がなされていました。家長や族長は一族の生活を保護する義務があり、構成員たちは一族の問題や緊急事態に長を補佐する義務を負いました。
裏切り者は死刑。
長は司法官の役割も担っており、若い男性は長を補佐して戦い、戦利品が分け与えられました。
まだ貴族や司法制度というものは存在していませんが、フェーデの起源が垣間見えます。
フェーデは仇討が仇討を引き起こしかねないため、相手を根絶するまで闘争が繰り広げてしまう危険性があります。
負傷者側から仇討ちされないために、負傷者に賠償金を支払うことで和平を結ぶという手段が取られるようになりました。金額は、負傷者側が満足する額を用意しなければならないとされています。
和平は金で買うものでした。
中世
フェーデは発展すると大規模な戦争となり、地域は壊滅的な損傷を受けます。
身代金や略奪目的でフェーデが広く行われるようになってしまいました。
なかなか成功しませんでしたが、10世紀になると、教会はこの自体を食い止めようとフェーデを制限しようと神の平和運動を行います。
木曜日から日曜日の夜までは休戦するように求め、これを成功させます。


カロリング朝時代の国王は、フェーデを制限しようと苦心していたことがわかっています。
1235年に神聖ローマ皇帝フリードリッヒ二世(Friedrich II.)がマインツのラント平和令(Mainzer Landfriede)を公布し、フェーデを部分的に制限しました。
フェーデを行うためには手続きが必要となります。
フェーデを行うにはその都度、決まった形式の宣戦布告(Fehdebrief)をして始めることが騎士の守るべき道徳となりました。宣戦布告でフェーデを行う場所と日時を公開しなければなりません。
礼拝所は通常、集落の中で唯一の石造りの建物で防御性に優れていました。
戦争は民衆の生活を脅かすものなので、有事の際に干し草や藁、作物の種子、家具などを礼拝所に保管することを定めた法令があります。
フェーデを行うための手続きがいろいろ面倒になったとはいえ、戦うことが騎士の本分。なにかとかこつけてフェーデは行われていました。
盗賊騎士の存在
商人たちの旅路を襲ったり、商品を取り上げたりする行為は、しばしばフェーデに発展しました。
騎士たちは、敵対する都市民の財産を戦利品とみなしています。
困窮と貧困からくる盗賊騎士は実際にはほとんどいません。裕福な領主がフェーデを行っていることもあります。



教会領主でさえ、強盗や放火、殺人などのフェーデを繰り広げていたよ



フェーデを禁止する立場じゃないのかよ!


フェーデの戦い方
戦いの前に敵軍が成立し、その後、選ばれた騎士たちによる予備選が行われ、最後の総力戦が行われました。
フェーデでは騎士道精神と公正さが優先され、誰もが栄光を追い求めることが可能な場所でした。
フェーデの終焉
14世紀以降、慣習的な戦法を厳格に守った結果、騎士の軍隊は大敗を喫することになります。
1495年、ドイツ国王と後の皇帝マクシミリアン一世(Kaiser Maximilian I.)が永久ラント平和令(Ewiger Landfriede)を制定し、訴訟法としてのフェーデは禁止されます。
紛争は暴力ではなく、法廷で法律に基づいて非暴力的に紛争解決が行われるようになりました。
戦争と言う形での領主間の争いはその後も続きますが、訴訟法としてのフェーデはそれ以後ほとんど行われなくなりました。



司法が機能するようになったことで、フェーデが消滅したよ。