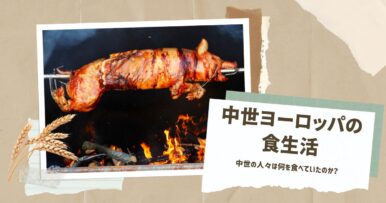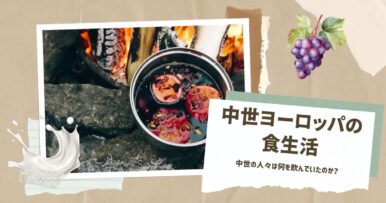昔の日本と同様に、ヨーロッパでも基本的に上流階級の母親は自分で母乳を与えず、乳母に子どもの世話を任せました。
乳母は農民の出身が多く、時には実の母以上に子どもと強い絆を結ぶこともありました。
子どもたちの教育が本格的に始まるのは、小学校入学の年齢と同じくらいの7歳から。将来の役割を見据えた厳しい修行が始まります。
 城山塔子
城山塔子男の子は「戦士=騎士」になることが期待され、女の子は家事だけでなく、兵士たちを治療するために民間医療の知識を叩き込まれたよ。
本記事では、以下の点を詳しく見ていきます。
- 男の子が騎士になるために受けた教育
- 女の子が良き貴婦人となるために受けた教育
7歳までの男女共通の生活


男の子も女の子も、幼児のうちは「婦人の間(Kemenate)」で母親や乳母、侍女たちと暮らしました。
父親と食卓を共にすることはなく、母や乳母が初期教育を担当します。
おもちゃは木や粘土で作られた素朴なもの。
- 男の子
-
棒馬(馬の頭をつけた木の棒)や駒、輪投げ、鬼ごっこ、吹き矢、ボール遊び。
これらは後の武術訓練の模倣にもなっていました。
- 女の子
-
人形や鏡道具を使った「ままごと」遊び。家庭生活を学ぶ遊びです。



子どもたちの遊びって、今とそんなに変わらないのね。
夏は水遊びやイチゴ狩りも楽しみました。
遊びは単なる娯楽ではなく、将来の役割を先取りする訓練でもありました。
男の子の教育―パーゲから騎士へ


7歳になると、男の子は騎士になるための本格的な教育が始まります。
騎士になるための修行は以下のように大きく2段階に別れます。
- パーゲ(小姓:Page):7~14歳
- クナッペ(従者:Knappe):14歳~21歳頃まで
パーゲ(Page)としての修行
パーゲ(小姓・騎士見習い)としての第一歩は、父親や兄、あるいは教育係から、雅(höfisch)な立ち振る舞いを学ぶことでした。
多くの場合、子どもは別の信頼できる騎士の城に送られ、そこで修行しました。



特に王侯貴族の宮廷は修行場所として人気があったよ。そこで君主に目をかけてもらえば、出世も早かったからね。
これは単に教育を受けるという目的だけでなく、以下のような側面もありました。
- 有力者と人脈を築く
- 同盟関係を維持するための「人質」として
パーゲの主な仕事は、食事の給仕、使い走り、客人の持ち物(武器や馬)の管理など。
この時期に乗馬、水泳、弓道と行った基礎的な武術も身につけました。



今川氏のもとで幼少期を人質として過ごした徳川家康も、武術や教養を叩き込まれたし、同じ人質仲間だった北条氏規と生涯交流を持ったのと似ているね。
クナッペ(Knappe)としての修行
男の子は12~14歳以降は母親や乳母から引き離され、クナッペ(従騎士)として主人に仕え、より実践的な訓練が始まります。
訓練内容は乗馬、水泳、狩猟、格闘、弓術、槍投げ、フェンシングなど多岐にわたり、騎士にとって大切な武器や甲冑の手入れの仕方も学びました。
ランス(槍)を持って走る訓練や、剣・メイス・戦斧などを使った実践的な練習も行われました。
利き手ではない手でも武器を扱えるように鍛えられ、実用的な練習として食料調達もできる狩猟が好まれました。
従者の重要な役目は、主人の身の回りの世話です。
武器の手入れから甲冑の装着補助、そして戦場では主人のすぐ傍で従軍し、危険な任務に身を投じました。
そのため、未熟なうちに命を落とす少年も少なくありませんでした。
それでも戦争による混乱の中、主人の傍を離れることを許されず、死の恐怖が迫りくる中、果敢に戦うことが要求されます。
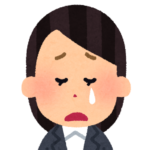
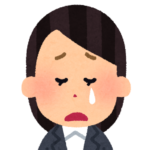
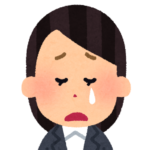
まだ未熟なうちから戦場に出なければならないなんて、騎士になるのも命がけなのね。
騎士叙任式へ
パーゲや従者として修行を積み、戦場で十分な軍事的能力があることを示し、人格的にも優れていると認められれば、、晴れて「刀礼(Schwertleite)」を経て正式に騎士に昇格しました。
もとは武器を贈るだけの簡単な儀式でしたが、やがてキリスト教的な意味を帯び「騎士叙任式(Ritterschlag)」として確立します。
21歳頃になると騎士の仲間入りを果たし、給仕仕事から卒業しました。


この騎士叙任式の広まりには地域差があり、ドイツでは14世紀になってようやく登場した儀式と言われています。
しかし騎士の仲間入りをするための「刀礼の儀式」は、それ以前から存在しています。
騎士に必要な学問と教養
騎士教育は立ち振舞と武術だけではなく、学問や語学も含まれていました。
- 神学・音楽
- 語学(特にフランス語)
- 読み書き(鉄筆とワックス板で練習)
- 数学(領地管理に必要な程度)
中世初期の頃はまだ、読み書きが出来るのはほとんど聖職者に限られており、一部の王ですら署名しかできませんでした。



騎士たちはほとんど文盲だったと考えていいよ。
文字が読めない一方で、領地の管理や他国との交渉のための話す語学力は重要視される傾向にありました。
読み書きそろばんは聖職者に任せる仕事とされており、それよりも他国と交渉するための会話力が何より大切とされていました。
騎士はしゃべることはできても読み書きはできないことのほうが多く、詩人のヴォルフラム・フォン・エッシェンバッハ(Wolfram von Eschenbach)はフランス語を書くことはできませんでしたが、話すことはできたようです。



漢文は読めても中国語は話せない日本の平安貴族とは逆ね。
時には有名な教師のもとで、自由七科(die sieben freien Künste:文法、修辞学、弁証法、音楽、算術、幾何学、天文学)を学ばせることもありました。
15世紀まで書物は大変高価で貴重なものであり、鎖で固定されていました。
本を読むよりも講義を聴いて学ぶ「耳学問」が主流でした。
日本の場合は、『子曰く…』と本を読むシーンを時代劇で見かけるように目学問です。現在でも教育において、耳学問の西洋と目学問の東洋との間に違いが見受けられます。
女の子の教育―少女から貴婦人へ


女の子の重要な役割は、結婚して子供を産むことでした。
しかし教育も軽視されていたわけではなく、母親や親戚の女性たちが教師となって家庭で教育を施しました。
貴族の少女の教育
婦人の間(Kemenate)が教室となり、母親や親戚の未婚女性や未亡人も先生となり、以下のようなことを学びました。
- 糸紡ぎ・裁縫・刺繍
- 音楽や礼儀作法
- 乗馬
これらは家政を支えるための実用的なスキルであり、祝祭の衣装などを自ら用意する役目もありました。
ニーベルンゲンの歌には、クリームヒルトが夫のために豪華な衣装を用意する場面が描かれています。
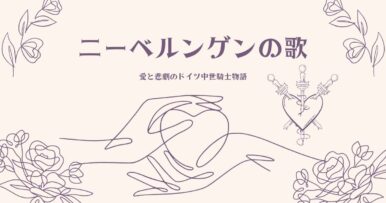
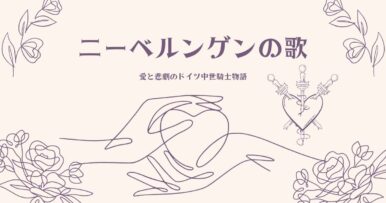
宮廷での教育
少年たちと同様に、少女たちも親元を離れ、教育のために他の宮廷に送られることもありました。
そこで給仕の仕事をしたり、いろいろな仕事を分担して請け負い、常に城主夫人に仕え、傍にいました。
武が重んじられた男の子に比べ女の子の方が教養レベルが高く、多くの女の子が読み書きができました。この時代に優れた文学作品を残した女性もいます。
民間医療と薬草知識
中世の城には医者がいないのが普通だったため、女性は「応急処置」の知識を学ぶことが非常に重要視されました。
城の庭園で薬草(ハーブ)を育て、その効能や使い方を教わります。
例えば、ハーブには以下の薬効があります。
- カモミール
-
鎮静効果
- セージ
-
喉の痛みに
- タイム
-
咳止め


マルクスブルク城のハーブ園
城の庭園で観葉植物や食用植物の他に薬草を育てることを学びます。
食用植物は籠城戦のときの貴重な食料になり、薬草は傷ついた兵士たちのための治療薬として用いられました。
Marion Halft, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons
社交界デビューと結婚
結婚適齢期(当時は10代前半)になると、父の主君の社交場にデビューします。
ここでのパーティーは結婚相手を見つける絶好の機会の場でありましたが、その選択権は娘にはありません。
結婚相手を見つけてくるのは両親であり、結婚相手は両親または親戚筋によって決められました。
女の子は修道院に入らない限り、同じ地位の貴族と結婚し、ほぼ政略結婚でした。
女性の地位は低く、夫は妻を従わせる権利を持ち、暴力を振るうことも当然とされていました。
それがたとえ本当に愛している妻であっても、当然のように暴力を振るうDVが当たり前の世界です。
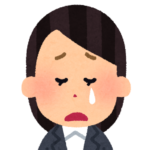
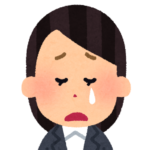
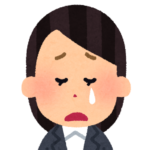
当時の女性たちが騎士物語のヒロインに憧れた気持ちがわかるわ。恋愛結婚なんて夢物語だったのね。



でもその騎士物語に登場する理想の騎士でさえ、妻を殴ってるんだよね
中世の「ミンネ(宮廷的恋愛)」という理想化された恋愛文化は、現実の厳しい女性の境遇と強いコントラストを成していました。


まとめ
ここまで見てきた教育は、あくまで貴族層に限られたものです。
農民の子どもは幼少期から畑仕事や家畜の世話を手伝い、教育の機会はほとんどありませんでした。
教育を受けられるかどうかは、身分によって大きく隔たれていたのです。
中世ヨーロッパにおける貴族の子供の教育は男女で大きく方向性が分かれていました。
- 男の子:戦場に立つ騎士となるため、武芸と語学を中心とした修行
- 女の子:良き貴婦人となるため、家政・礼儀作法・薬草学を重視
厳しい現実の中で育った少年少女の姿を知ると、騎士物語や宮廷文化に描かれる理想がどれほど夢の世界であったかが浮かび上がってきます。
日本との比較
日本の武士家系の子どもも、幼少期に遊びや模倣を通じて武芸を学び、元服によって成人と認められました。
- 武家の男子:馬術・剣術・弓術
- 武家の女子:家政・礼儀作法・芸事



こうしてみると、日欧の教育には共通点も多いのね。